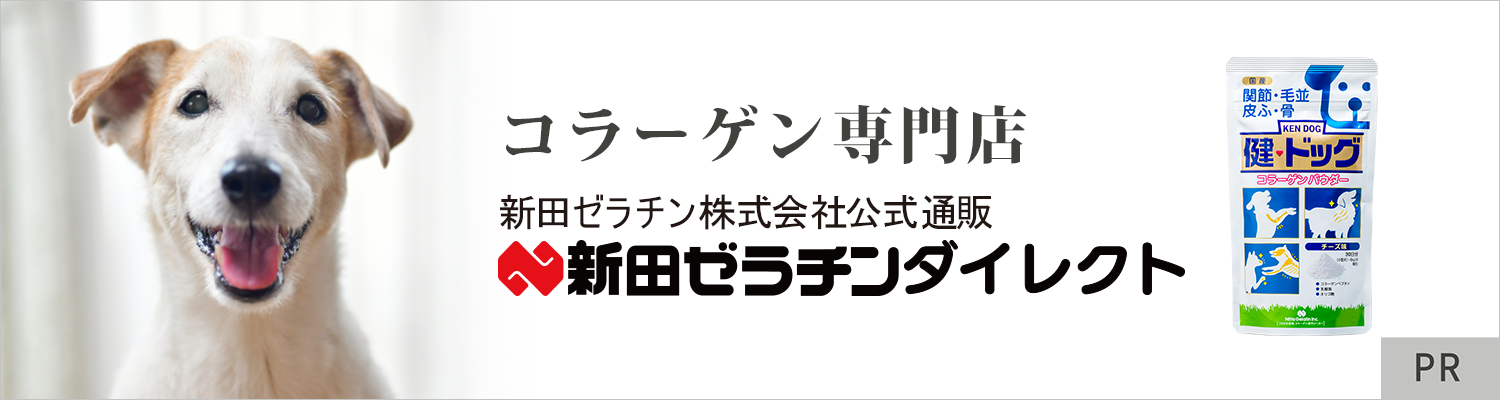犬(動物)にとって食事以上に大切なものは?

食事に含まれる五大栄養素(タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラル)は、エネルギー源や体を作るための材料などになり、とても大切です。愛犬の健康のために栄養バランスを考えて食事を選ぶ方も多いでしょう。また、食事は愛犬の楽しみのひとつでもあり、おやつにわくわくする姿はとても可愛く、愛犬とのコミュニケーションツールとしても利用されます。
この食事以上に大切なもの、それは、「水」です。
水は五大栄養素には含まれませんが、水がなければ食事に含まれる栄養素は体内で働くことができません。食事(栄養)の摂取量が足りないと健康を損ねますが、水は摂取できないとより早期に深刻な健康問題を生じてしまいます。
今回は、犬(動物)にとっての水について、その役割を中心に解説します。
体内の水分
水は体内で最も豊富な物質であり、動物の体の約 7 割は水で構成されています。残りの3割はタンパク質や脂肪、ミネラルなどです。
この 7 割の水は体内のどこに含まれているでしょうか?水と同じ液体である血液を思い浮かべる方も多いと思います。この血液中の水分より多いのが細胞内の水分です。肝臓の細胞にも筋肉の細胞にも脂肪細胞にも水は含まれています。
体内における水の役割
水は体内でとても重要な役割を担っています。
水がなければ以下の働きが行われず、それは生命にとって致命的です。
<液体として物質を運搬・移動>
水は流れることができるため、血液に含まれる赤血球(酸素)や栄養素を必要な組織に運び、二酸化炭素や老廃物のような不要な物質を排出する組織(肺や肝臓、腎臓など)に運ぶことができます。細胞内では物質の合成や分解などさまざまな化学反応が行われていますが、ここでも物質の移動に水が役立つだけでなく、加水分解など「水」が加わることで起こる化学反応もあります。
<溶媒として物質を溶解>
水は優れた溶媒(物質を溶かす液体)です。
血液の水分中には、アルブミンのようなタンパク質、グルコース(ブドウ糖)のような糖質、ナトリウムやカルシウムのようなミネラルなど、さまざまな物質が溶けています。物質が固まって沈殿することなく、溶けているから血液の流れによって運ぶことができます。
同様に細胞内でも、さまざまな物質が溶けていることで化学反応(代謝反応)を起こすことができます。例えば、エネルギー供給物質である ATP(アデノシン三リン酸)は、細胞内の解糖系やクエン酸回路で次々と化学反応が進み合成されます。このような反応も物質の水への溶解が必要です。
<体温調節の役割>
水は温まりにくく冷めにくいという性質があります。気温が上がっても、体の約 7 割が水で構成されている動物の体温がすぐに上がることはありません。これは温まりにくいという水の性質だけでなく、人間の場合は汗によって、犬の場合はパンティングという口を開けた浅くて速い呼吸によって水分を蒸散させる体温調節機構が働いているからでもあります。水は蒸散時に熱を奪って蒸発していくため、これも水の性質を利用した体温調節です。
このように水は生きていくために必要不可欠です。
水分出納
水分を体内に取り入れる方法は、飲み水として摂取する以外に食事に含まれる水分からも摂ることができます。缶詰のようなウェットフードは 7~8 割が水分です。カリカリのドライフードにも 1 割前後の水分が含まれています。つまり、犬が 100 グラムのウェットフードを食べれば、70~80 グラムの水の摂取になり、100 グラムのドライフードを食べれば、10 グラム前後の水を摂取することになります。
また、水は摂取以外に、体内の代謝によっても作り出されます。三大栄養素であるタンパク質、脂質、炭水化物はエネルギー源となる栄養素です。食事に含まれる三大栄養素は、消化吸収された後、細胞内で代謝され、ATP が作られます。この時に水も生じ、これを代謝水と呼びます。例えば、炭水化物であるデンプンは、消化管で消化(分解)されブドウ糖になり体内に吸収されます。その後ブドウ糖は細胞内に運ばれ、そこで解糖系、クエン酸回路、そして電子伝達系を経て、ATPと二酸化炭素と水(代謝水)を生成します。代謝水は必要な水分量の 1 割近くを占めています。
体から水が出ていく主なルートは尿です。このほか、便や呼吸からも水は出ていきます。犬にも汗腺はありますが、人の汗のように水が出ていくルートとしての役割はあまりありません。
「水の出入り」という言葉のように、本来、水は出ていく方が先です。水が体内から出ていった分、体が水を欲し、動物は水を飲みます。
水の必要な量
犬の必要な水分量の計算方法はいくつかありますが、よく用いられる方法が体重から計算した 1 日エネルギー要求量(kcal)の数値をミリリットル(mL)にする方法です。例えば 1 日のエネルギー要求量が 300 kcal の場合、必要な水分量は 300 mL になります。
このように計算によって必要な水分量を求めることはできますが、犬の年齢や活動量、環境温度の違いなどによって実際の飲水量は大きく異なる場合もあります。暑さや運動などによりパンティングが増えると飲水量は増えますし、食事量が増えても飲水量は増えます。また腎臓病や糖尿病などの病気によって、あるいは薬の作用によって飲水量が増える場合もあります。塩分濃度の高い食事でも飲水量は増えます。ちなみに、犬は水が十分に飲める環境があれば、味付けの濃い人の食事を食べてしまっても、塩分(ナトリウム)の摂りすぎが問題になることは通常ありません。
一方、快適な環境下で静かに過ごしたり、食事の量が少なかったりすると、飲水量は減ります。缶詰のような水分の多い食事を食べた場合も、水を飲む量は減ります。
計算した量の水を飲まないからといって、無理に飲ませる必要はなく、逆に飲みすぎるからといって水を取り上げてもいけません。通常、犬は自分で必要量を摂取するようにコントロールしています。尿量が増え(体から出ていく水分量が増え)、体が脱水に陥りやすい病気の場合、飲水量を増やして脱水にならないように犬は調節していますが、ここで水の摂取量を制限してしまうと、脱水症になったり、病気が悪化したりするかもしれません。いつでも自由に十分量の水が飲めるようにしましょう。
尿路結石症や心臓病など一部の病気では摂取水分量を考慮した管理が行われる場合もあります。また、体調が悪くて必要量を飲むことができない場合もあり、病気の際はかかりつけの動物病院で相談しましょう。
水分が不足すると
体のおよそ 7 割が水分で構成されていますが、その水分の損失量が多いと健康を損ね、ひどい脱水に陥れば命に関わります。数週間食事が摂れなくても水があれば生存できる可能性はありますが、水がなければ数日で亡くなるかもしれません。
自由に飲める水があれば、健康な犬が水分不足になることはありませんが、病気により尿や下痢、嘔吐によって体内から出ていく水分が多く、それに見合う水分摂取ができない場合は水分不足(脱水症)になります。体重の減少は、減量(ダイエット)のようにエネルギー(カロリー)摂取量を減らした食事を続けていても起こりますが、食欲不振などにより短期で生じた体重の減少はほとんどが体から失われた水分の量です。愛犬の体調が悪くて体重減少も伴う場合は脱水症が懸念されるため、早めに動物病院に連れていきましょう。特に腎臓病など尿量の増えるような病気を持っている場合、脱水の進行が速く病気の悪化も起こりやすくなります。
水分過剰(水中毒)
水分不足は病気の際などよく問題になりますが、逆に水を飲みすぎて問題になることはあまりありません。通常、犬は水の摂取量を自分で調節できますが、長期に水の摂取ができなかった後など、反動で一気に大量に水を飲み、水中毒の症状が出る場合もあるようです。中毒症状では軽いふらつきから、重篤になると溶血や昏睡に至る場合もあります。
水は常に与えられるものであり、水を愛犬へのご褒美、コミュニケーションツールとして利用する方はいないかもしれません。私たちは衛生的な水が当然のように手に入るた
め、水の摂取の大切さを忘れがちですが、食事と同等以上に水は大切です。
愛犬の飲み水のためにミネラルウォーターや蒸留水のような特別な水が必要だとは思いませんが、毎日、清潔な容器で新しい水道水を、いつでも十分量飲むことができるように、自由に水飲み場にアクセスできるようにしましょう。
水を飲み切って、あるいはこぼれて水の容器が空になっていたり、ペットシーツや敷物が吸い取って飲めない状況になっていたりなど、水がなくて愛犬が寂しい顔にならないように注意しましょう!