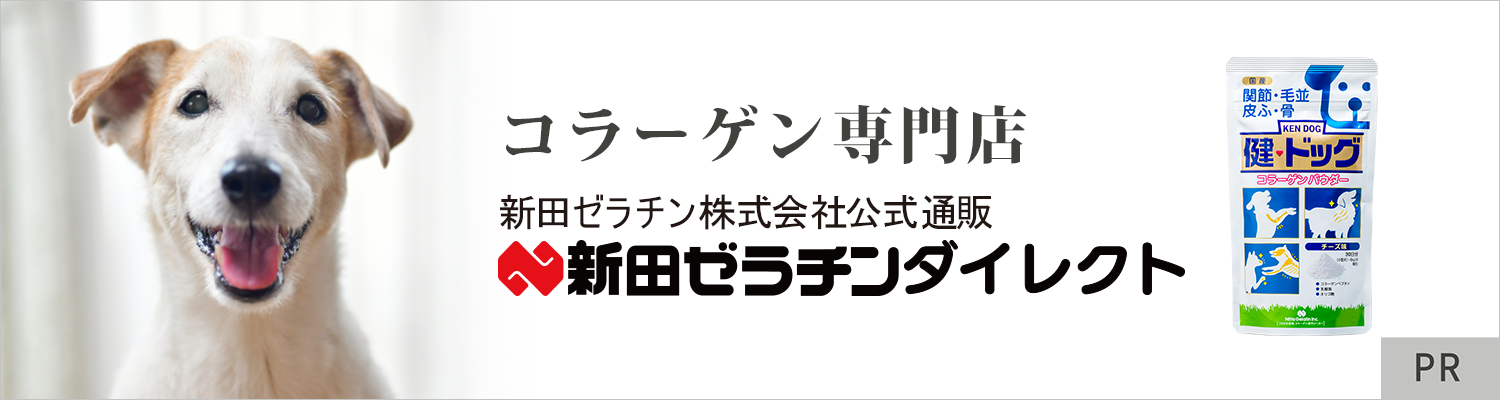人と犬の食事のたんぱく質量の違い

たんぱく質は肉や魚に多く含まれ、とても大切な栄養素です。
肉食であるオオカミを祖先に持つ犬は、私たち人間と暮らしていく中で雑食への適応が進みましたが、人間よりたんぱく質の要求量は高い動物といわれています。
みなさんの愛犬の食事のたんぱく質量はどのくらいですか?人の2倍ですか?それとも3倍?
今回はたんぱく質について、そして人と犬の食事のたんぱく質量の違いについて解説します。
たんぱく質とは
たんぱく質は20種類のアミノ酸が、数十個から数千個も結合した物質です。20種類のアミノ酸のうち、体内で十分量を合成することができないため必ず食事から摂取しなければならないアミノ酸を必須アミノ酸といいます。体内で他の成分から作ることができるアミノ酸は可欠アミノ酸といいます。
人間の必須アミノ酸は9種類(ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リシン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、トリプトファン、バリン)で、11種類が可欠アミノ酸です。犬や猫の必須アミノ酸は10種類で、人間の必須アミノ酸にアルギニンが加わります。猫の必須アミノ酸はタウリンも含めて11種類とする場合もありますが、タウリンの構造はアミノ酸の条件であるカルボキシ基がなく、たんぱく質を構成するアミノ酸でもないため、ここでは猫の必須アミノ酸に含めていません。
たんぱく質はエネルギー源である三大栄養素のひとつですが、ほかの炭水化物や脂質と異なり窒素を含みます。これはたんぱく質の役割や代謝に大きな影響を与えています。
摂取したたんぱく質の役割
体内に存在するたんぱく質として思い浮かびやすいのは筋肉ですが、このほか、皮膚や被毛、軟骨もたんぱく質です。また、体内で物質の運搬や浸透圧の調節をするアルブミン、そして免疫機能などにかかわるグロブリン、消化管に分泌される消化酵素も細胞内で行われる代謝反応で働く酵素もたんぱく質です。これら体のたんぱく質は、遺伝子の情報に基づき20種類のアミノ酸が多数結合して作られます。摂取したたんぱく質の役割は、体のたんぱく質の材料であるこのアミノ酸を供給することです。
また、たんぱく質に含まれる窒素は、核酸の一部である塩基の合成などに利用され、炭素は糖新生に利用されてグルコースとなり各組織のエネルギー源になります。
たんぱく質の消化と吸収、そして代謝(細胞内の化学反応)
食物から摂取したたんぱく質は、消化管でアミノ酸が数個結合したサイズ(ペプチド)から完全に個々のアミノ酸になるまで分解され、その後体内に吸収されます。吸収されたアミノ酸は、肝臓や各組織で筋肉や酵素のようなたんぱく質の合成、そしてDNAのような核酸の合成に利用され、また、エネルギーとしても利用されます。体のたんぱく質は時期が来るとアミノ酸に分解され、このアミノ酸は再び新しいたんぱく質の合成に利用されたり、さらに分解されてアンモニアを生じたりします。アンモニアは窒素を含む化合物で、体にとって毒性が強いため、肝臓で毒性の弱い尿素に変換され、腎臓より尿として排泄されます。
たんぱく質の摂取が必要な理由
上記のように、体のたんぱく質はアミノ酸に分解されても合成に再利用されますが、一部は尿素となって体外に排泄されるため、たんぱく質の摂取は必要です。たんぱく質の摂取は、怪我や病気などで壊れた、あるいは失われた組織の修復や回復、そして免疫反応のためにも必要ですし、成長期のように新しい組織を形成する際は、より多くのたんぱく質が必要です。
良質なたんぱく質
たんぱく質は摂取量が十分でも、構成しているアミノ酸の一部が多すぎたり、逆に少なすぎたりと、アミノ酸バランスが悪いとよくありません。ほかのアミノ酸の利用にまで影響が及ぶため、たんぱく質を構成しているアミノ酸の種類や量は、動物にとって適切であることが重要です。食材単位でアミノ酸バランスが多少悪くても、食材の組み合わせによって、完成した食事単位ではバランスをよくするような対応が取れます。
また、たんぱく質の消化率も、動物にとって重要です。調理時間や調理温度、食物繊維やたんぱく質分解酵素阻害成分の存在はたんぱく質の消化率に影響を与える場合があります。
良質なたんぱく質は、たんぱく質を構成しているアミノ酸バランスがよく、各アミノ酸の量も十分に存在し、消化率も問題のないたんぱく質です。愛犬が健康な際は、たんぱく質が良質であることにそれほど神経を使わなくても構いませんが、消化器の病気やたんぱく質の制限が必要な病気の場合は、良質なたんぱく質を選びましょう。
たんぱく質(アミノ酸)の不足と過剰
たんぱく質の摂取量が不足すると、体内のたんぱく質の合成に影響がでます。不足の程度がひどい場合、皮膚や被毛に異常が生じ、体重が減り、アルブミンのようなたんぱく質も減少してしまいます。
タウリンは、メチオニンというアミノ酸から合成されます。猫は必要量を合成することができないため、食事にタウリンが十分量含まれていないと心臓や目の病気になる場合があります。犬は合成することができますが、一部の犬はタウリン欠乏を起こしやすく、たんぱく質の少ない食事の場合、メチオニンの摂取量も減るため、よりタウリン不足に陥りやすくなります。
一方、たんぱく質を過剰に与えた場合、体内で利用される以上の余分なたんぱく質は分解され、エネルギー源や脂肪に変換され、老廃物は腎臓より排泄されます。腎臓病の場合は、この老廃物の排泄がうまくできないため、たんぱく質の与えすぎは問題です。腎臓病の初期は症状があまりなく、定期的な健康診断で初めて腎臓の機能が落ちていることに気づく場合もあります。肉や魚を好む愛犬は多いと思いますが、与えすぎには気をつけましょう。
人や犬猫の食事のたんぱく質量の研究
人や犬猫のたんぱく質の必要量は、たんぱく質に含まれる窒素の量に着目し、摂取した窒素がどのくらい体内に取り込まれ、どのくらい排泄されたかを調べます。また、体重の増え方で調べる方法もあります。研究の際は、通常、消化の良いたんぱく質を用いて行われますが、実際の食事ではたんぱく質の消化率は下がるため、そこも考慮してたんぱく質の必要量は決められます。
動物はたんぱく質に含まれるアミノ酸を必要とします。たんぱく質の摂取量が少ない場合、アミノ酸の代謝を抑えるために酵素活性を下げます。すなわち、アミノ酸の分解を減らすようにします。ただし、この調節は肉食である猫はあまりうまく行えず、犬もラットよりうまくできません。このような代謝の違いが、食事のたんぱく質量の違いにつながります。
人と犬の食事のたんぱく質量を比較
日本人の食事摂取基準では、たんぱく質の基準には、推定平均必要量、推奨量、目標量が設定されています。推定平均必要量は、摂取不足の回避を目的として設定され、半数のものが必要量を満たすと推定される摂取量です。推奨量は、推定平均必要量と同様の目的ですが、ほとんどのものが充足している量です。目標量は、生活習慣病の発症予防のために現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量として設定されています。例えば、成人(30~49歳女性)のたんぱく質の推定平均必要量は、1日に40 g、推奨量は1日に50 g、目標量は、1日に13~20%エネルギー量です。
ドッグフードの総合栄養食の基準に採用されているAAFCO養分基準の場合、たんぱく質の基準には最小値が設定されています。この最小値は原料の利用率も考慮され、これは日本人の食事摂取基準では推奨量に近いと考えられます。成犬のたんぱく質の最小値は1,000 kcalあたり45 gです。この犬の最小値を比較するためには、先ほどの人のたんぱく質の推奨量をエネルギーあたりに換算します。
例に挙げた30~49歳女性の場合、推定エネルギー必要量は1日に2,048 kcal(身体活動レベルがふつうの場合)です。1,000 kcalあたりの推奨量にすると24 gになり、成犬のたんぱく質の基準値は人のおよそ2倍となります。同年代の男性の場合、1日の必要なたんぱく質量は女性より多いですが、エネルギー量も多く、エネルギーあたりに換算して比較すると、同様の結果になります。
犬の栄養基準はいくつか種類があり、今回のような基準値同士の比較でも、採用する基準が異なればその結果は異なります。さらに、基準値同士の比較ではなく、実際に食べた食事に含まれるたんぱく質の量を比較することになると、食べた食事の内容によって結果は異なると考えられます。
犬の食事のたんぱく質量は人間の2倍や3倍など、さまざまな数値を耳にすることがあるのは、比べた内容が異なることが理由かもしれません。
いかがでしたか?みなさんの愛犬の食事のたんぱく質量はどのくらいですか?アミノ酸バランスはよさそうですか?
「犬は人の〇倍のたんぱく質」は、比較した内容や方法によって結果は異なります。犬は人より多くのたんぱく質が必要ですが、あまり数値を気にせずに、ワンコは肉が好きだな~くらいで愛犬の食事タイムを楽しんでください。ちなみに、ワンコは人の3~4倍くらいのたんぱく質量が好きだそうです。
動物病院では、病気に応じてたんぱく質を制限したり、増やしたりするような栄養管理が行われます。動物病院より指示されたたんぱく質量は、愛犬の体調に合わせて獣医師が判断した量です。肉の量が心配な場合は、ネットで検索するより、その先生に直接確認した方が早めの解決につながります。納得、安心して、愛犬の栄養管理は行いましょう!
追記
今回、ご質問をいただきこのコラムの内容にしました。話題のAIにこの質問をぶつけてみましたが、代謝体重の式を体重の式として説明したり、子犬の情報を成犬の情報として説明したり、いろいろ混乱しているようです。今後、訂正されると思いますが、今の時点ではAIの情報を鵜呑みにしないようにしましょう。
愛犬愛猫の食事にかかわることです。誤った食事にならないように、一緒に気をつけましょう~